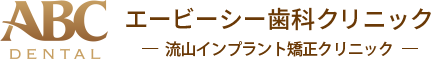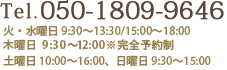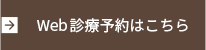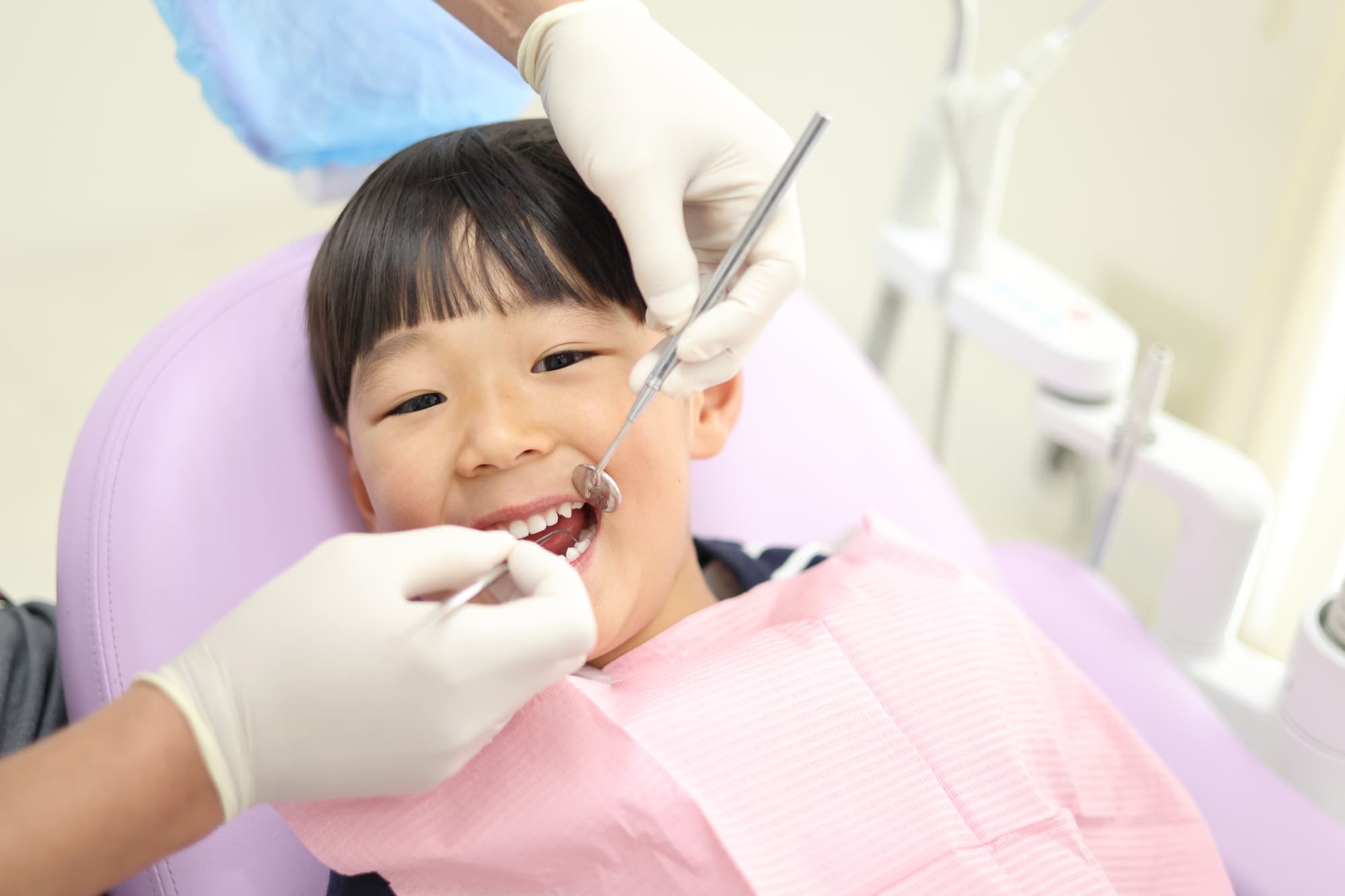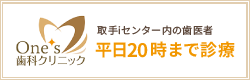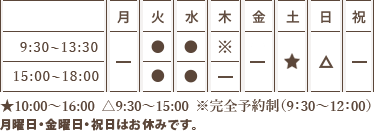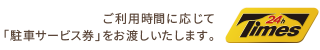床矯正とはどんな矯正方法?メリットや対象年齢、費用も
こんにちは。千葉県流山市にある歯医者「ABC歯科クリニック」です。
歯並びや噛み合わせの悩みは、多くの人が抱える問題です。特に、子どもの歯並びの乱れは、早期の対処によって将来的な影響を大きく軽減することができます。そんな中で注目を集めているのが、床矯正(しょうきょうせい)です。
床矯正は、成長期の子どもに使用することが多く、従来のワイヤー矯正とは異なるアプローチをとる点が特徴です。床矯正は歯を無理に動かすのではなく、顎の成長を促してスペースを作りながら歯並びを整えていくという身体に優しい矯正方法です。
この記事では、床矯正のメリットやデメリット、対象年齢、そして費用について、詳しく解説します。子どもの歯並びでお悩みの保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
床矯正とは
床矯正とは、取り外し可能な装置(床装置)を用いて歯列を広げ、歯がきれいに並ぶスペースを作り出す矯正方法です。主に成長期の子どもを対象に行われ、顎の成長を利用しながら理想的な歯並びを実現します。
ワイヤーやブラケットを使う従来の矯正方法とは異なり、自然な成長の力を利用する点が大きな特徴です。
床装置はプラスチック製のプレートと金属製のバネで構成されており、上顎または下顎に装着します。ネジがついていて、保護者が一定の間隔でネジを回すことで少しずつ顎を広げていきます。
これにより、歯が並ぶためのスペースが徐々に確保され、無理なく歯列が整っていきます。
床矯正のメリット
この見出しでは、床矯正の代表的なメリットについて詳しく解説します。
顎の成長を促しながら矯正できる
床矯正の最大のメリットは、子どもの顎の成長を促しながら歯列を整えられる点です。床装置は骨に穏やかに力をかけるため、身体への負担が少なく、痛みも軽いと言われています。
取り外しが可能で衛生的
床矯正で使用する装置は自分で取り外しが可能なため、食事や歯磨きのときは取り外して、清潔な状態に保つことができます。固定式の矯正装置に比べて虫歯や歯周病のリスクが低くなるのは、床矯正の大きなメリットでしょう。
また、装置が汚れた場合も簡単に洗浄できるため、衛生管理がしやすいという利点があります。
日常生活への影響が少ない
床矯正の装置は取り外せるので、発音や会話への影響が軽減され、子どもの自尊心や社会生活に支障が出にくいのもメリットです。
ただし、装着時間を守らなければ治療が長引いたり効果が出にくくなったりします。保護者と子どもの両方の理解と協力が不可欠です。
床矯正のデメリット
ここでは、床矯正の注意点やデメリットについて解説します。治療を始める前に知っておくことで、失敗や後悔を防ぐ手助けになるでしょう。メリットと合わせて正しく理解することが大切です。
装着時間を守らないと効果が出にくい
床矯正は取り外しができる利点がある一方で、決められた装着時間を守らなければ十分な効果が得られません。多くの場合、1日12〜14時間以上の装着が必要とされています。
子ども自身が装着を嫌がったり忘れたりすると、治療が長引いたり、効果が不十分になったりする可能性があります。そのため、家族でしっかりとモチベーションを維持しながら取り組む姿勢が求められます。
適応できる症例が限られている
床矯正は、主に顎の成長を利用するため、対象となるのは成長期の子どもに限られるケースが多いです。大人や、すでに顎の成長が止まっている子どもには効果が期待できない場合があります。
また、重度の歯列不正や噛み合わせの異常がある場合には、床矯正だけでは対応しきれず、他の矯正治療と併用する必要が出てくることもあります。
話しにくさや違和感を覚えることがある
床矯正の装置は口の中に入れて装着するため、装着初期には話しづらさや異物感を覚える子どもも少なくありません。特に、会話や食事のときに気になることが多く、慣れるまでに時間がかかる場合もあります。
また、装置が合わなくなると痛みを感じることもあり、定期的な調整が必要です。こうした点を踏まえて、治療の継続には本人の意志と家族のサポートが重要になります。
床矯正の対象年齢
床矯正は、すべての年齢に対応できるわけではありません。ここでは、床矯正の対象年齢やその理由について、詳しく解説します。時期を逃さずに治療を始めましょう。
小学校低学年〜中学年
床矯正がもっとも効果を発揮するのは、顎の成長が活発な小学校低学年から中学年(おおよそ6歳〜10歳)です。この時期は、乳歯から永久歯への生え変わりが進み、顎の骨も柔らかいため、床装置による拡大がスムーズに行えます。
歯がきれいに並ぶためのスペースを確保しやすく、将来的に抜歯を避けられる可能性も高くなります。
床矯正を適切なタイミングで開始することにより、成長とともに自然な歯並びが形成されやすくなります。これにより、中学生以降に本格的な矯正が必要になった場合でも、期間を短くできたり、大掛かりな治療が不要になったりする可能性があります。
また、顎の骨格に関わる問題を早期に改善できることは、噛み合わせだけでなく、顔貌や発音などにも良い影響を与えるとされています。
成長が止まった後の床矯正は難しい
中学生以降や大人になってからでは、顎の骨が硬くなっているため、床矯正による拡大が難しくなります。そのため、この時期以降はワイヤー矯正やマウスピース矯正など、他の方法を検討する必要があります。
床矯正を検討されている方は、歯科医師と相談のうえ、早めに方針を決めることが大切です。
床矯正の費用
床矯正には健康保険が適用されないため、歯科医院の方針や地域、症例の難易度によって異なります。実際にいくらかかるのかは、事前に確認しておきましょう。
床矯正の一般的な費用相場は10万〜40万円程度です。装置の製作費や基本的な調整費用を含んでいることが多いです。
ただし、複数の装置を使う場合や治療期間が長引く場合は追加料金が発生することもあります。初診相談料や検査料が別途必要な場合もあるため、事前の確認が大切です。
月々の調整料が別でかかるケースもある
床矯正では、装置の効果を保つために定期的な調整や診察が必要です。多くの歯科医院では1回あたり3,000円〜5,000円の調整料が発生します。
治療期間や通院頻度によって合計金額は変わるため、治療前に全体のコストを見積もっておきましょう。
医療費控除の対象になることもある
床矯正を行う目的が治療であれば、医療費控除の対象になる可能性があります。美容目的でなく、発音や噛み合わせの改善を目的とした治療であることが条件となります。
医療費控除を受けるには領収書が必要となるため、費用を支払う際は忘れずに受け取っておきましょう。控除の申請により、実質的な負担を軽減できる場合があります。
まとめ
床矯正は、子どもの顎の発達を利用して、自然な形で歯並びを整えることができる矯正方法です。取り外し可能で衛生的、日常生活への影響も少ないというメリットがありますが、装着時間を守らなければ効果が出にくく、適応できる症例に限りがあるという注意点もあります。
費用は10万円〜40万円が一般的な相場であり、定期的な調整料や追加費用についても把握しておくことが大切です。医療費控除の対象となる場合もあるため、治療目的であることを明確にし、必要な書類をきちんと保管しておくとよいでしょう。
子どもの将来を見据えた矯正治療を考えるうえで、床矯正は選択肢のひとつとして非常に有力です。メリットとデメリットを正しく理解したうえで、歯科医とよく相談しながら、お子様に合った治療法を選びましょう。
床矯正を検討されている方は、千葉県流山市にある歯医者「ABC歯科クリニック」にお気軽にご相談ください。
当院では、マウスピース矯正やインプラント、一般歯科、予防歯科、審美歯科など、さまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web診療予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。